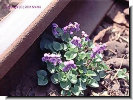イソスミレ (磯菫) [別名:セナミスミレ、イソタチツボスミレ、ハマタチツボスミレ]


石川県 2008年4月3日


新潟県村上市 2006年5月3日


新潟県上越市 2013年5月9日


青森県むつ市 2008年5月10日
| 分類 |
タチツボスミレ類 |
| 学名 |
基本種 |
Viola grayi Franchet et Savatier Published in: Enum. Pl. Jap. 2: 288. (1878) |
| 変種 |
|
| 品種 |
|
| 異名 |
Viola senamiensis Nakai, 1939 Published in: Journ. Jap. Bot., 15: 405. (1939) |
| 由来 |
grayi : 人名に由来する A. Gray, 1810-1888 アメリカの植物学者 |
| 外語一般名 |
【英】wonder violet |
| 茎の形態 |
有茎。 |
| 生育環境 |
寒冷な地方の海岸に咲き、砂浜と土が切り替わる(混じる)境界に多い。 |
| 分布 |
国内 |
太平洋岸では北海道日高から青森県八戸、日本海側では北海道後志支庁から鳥取県東部までとされる(情報が少し古い)。 |
| 海外 |
(日本固有種) |
| 補足 |
近年、北海道の太平洋側でも確認されている。 |
| 花の特徴 |
形状 |
タチツボスミレより大輪。花弁が横長でどっしりした形状になる。 |
| 色 |
濃いめの紫色。ただし、太平洋型は淡紫色。 |
| 距 |
太い白色。 |
| 花期 |
遅め。 |
| 花柱 |
棒状、柱頭が少し曲がる。 |
| 芳香 |
香りがあるとする資料がある(未確認)。 |
| 補足 |
側弁は無毛。 |
| 葉の特徴 |
形状 |
心円形。内側(表から)巻き込む。鈍頭。表裏とも無毛。 |
| 色 |
全体が明るく濃い緑色。 |
| 補足 |
厚く強い光沢がある。萼片は三角形で無毛。托葉は櫛の歯状に切れ込む。 |
| 種の特徴 |
形状 |
光沢がある黒褐色の楕円形(2mm程度)。 |
| 色 |
 |
| 補足 |
| 根の特徴 |
褐色で、真っすぐ下方に伸びる。 |
| 絶滅危惧情報 |
環境省【絶滅危惧Ⅱ類(VU)】  、北海道:準絶滅危惧種、秋田県:絶滅危惧Ⅰ類、山形県:絶滅危惧Ⅱ類、新潟県:絶滅危惧Ⅱ類、富山県:絶滅危惧Ⅰ類、福井県:絶滅危惧Ⅱ類、京都府:絶滅危惧Ⅱ類、鳥取県:絶滅危惧Ⅱ類 、北海道:準絶滅危惧種、秋田県:絶滅危惧Ⅰ類、山形県:絶滅危惧Ⅱ類、新潟県:絶滅危惧Ⅱ類、富山県:絶滅危惧Ⅰ類、福井県:絶滅危惧Ⅱ類、京都府:絶滅危惧Ⅱ類、鳥取県:絶滅危惧Ⅱ類 |
| 基準標本 |
セナミスミレ : 新潟県岩船郡上海府村(現村上市)1938/05/09 by Mituo Nagasawa(別説:牧野富太郎博士 1928) |
| 染色体数 |
2n=20 |
| 参考情報 |
|
| その他 |
生育地が極端に減っているため、保護が必要と言われている。
Viola semamiensis という学名を使用している資料を見つけた。V. senamiensis のミスタイプと思われる。それは別として、緻密な研究で知られる中井猛之進先生 が、イソスミレとは異なる種として発表したことから発生しているので悩ましい。現在はsynonymとして扱われている。 が、イソスミレとは異なる種として発表したことから発生しているので悩ましい。現在はsynonymとして扱われている。
京都府立大(生命環境科学研究科)の研究報告のよると、イソスミレの起源について、北海道や日本海側の個体(DNAのマイクロサテライト部)を比較した結果、「内陸のスミレが変異して、日本海側の海岸から全国に広がったと推定できる」とされた。
|
 |
 |
 |
太平洋型:淡い色で花弁は細め
← 大きめの株になる
「原色日本のスミレ*(出典:G001)
」によりますと
根はかなり深くて大きいようです
|
 |
日本海型:花弁は丸くふくよか
とても長生きです
現役の線路沿いに咲いています
繁殖力は十分にあるのですね
|
新潟県新発田市(旧 北蒲原郡) 2001年4月29日


石川県 2004年5月2日
春、イソスミレに出逢いたいと、長野から新潟(糸魚川)まで相当無理して移動したのに叶いませんでした。なのに、秋、全くの偶然で出逢ってしまう…。ままならないものです。
アレッ、タチツボスミレかな!?でも、花がかなり大きくて、第一、こんな海岸の砂地に生育するかな?茎の立ち上がり具合が違う、葉もしっかりしている。もしかしたら、イソスミレだったりして…。わぁ、株がこんもりとまとまっている。
三石町は、日高山脈襟裳国定公園に含まれる静内町と河浦町間の海岸線の町。札幌方面から見て日高耶馬渓の手前で内陸に入ると、アポイタチツボスミレなどの固有種で有名なアポイ岳があります。ただ、札幌近辺で道産子相手にアポイ岳の話をしても「知らない」とのことでした。植物愛好家の間限定で有名ということらしい!糸魚川に続いて、かなり無理をしたのですが、札幌から足を延ばした甲斐がありました。
セナミスミレという別名の由来となった海岸で、日本海型のイソスミレが細々と残っているとのこと。知り合いに概要をこっそり教えていただきました。
1999/11/12
やっと、すみれの季節に新潟を訪ねることができました。海岸線で半径50m前後の小規模の群落を見ることができたのですが、うわさ通り、細々と残っているという感じでした。その他に海岸線の道路沿い、駅構内の線路の敷石で見ることができました。イメージは丸くて大きくて明るいすみれです。
すみれは多年草ですが、株の寿命は一般に数年程度。でも、イソスミレは10年を超えて同じ株が充実して、大きな株に成長する。繁殖力もある…、問題は護岸工事や乱獲だということになります。「やはり浜におけ、イソスミレ」、「写真撮っても株取るな」ということでしょう。
2001/05/01
今年、比較的大きな自生地に辿りつくことができました。しかしながら、写真で見た規模より縮小しているイメージ。もう一つ感じたことは、地元の方々にとっては何でもない(ありふれた)植物なのだという点でした。すぐ近くまで4WD車両が走り回り、海岸はゴミだらけ。こんなものなのでしょう。でも、できるだけ、そっとしておきたいと強く感じたものでした。
2004/07/27
主要な自生地である新潟には、タチツボスミレ類が多く生育していますが、複雑に交雑しているとともに、環境への適応の結果と思われる変化が認められています。実際、ムラカミタチツボスミレやイワフネタチツボスミレは普通に見られます。また、イソスミレが海岸から離れて内陸に近づくと、葉の光沢が無くなるというような変化があるようです。
2006/05/10
レッドデータブック情報に記載されている都道府県(秋田、富山、福井、京都、東京)を分布図に追加することとしました。ただ、東京については、余りに不思議な感覚があった訳ですが、詳細を調べると「伊豆諸島」とあり、それなりに納得したものです。ただ、ツヤスミレの別名という可能性もあり、相当に怪しい情報かも知れません。
2008/02/28
少し木化した首のような地下茎(?)が砂から伸びているのを見ました。掘り返した訳ではないので、これ以上は書籍からの情報だが、水分の吸収目的もあって、地下部は非常に太く、根は大きく枝分かれしているそうだ。根は1m近くまで生育するということです。葉はやはり厚めで、丸くしっかりしていました。
2001/04/06


石川県 2008年4月3日
この自生地は2回目だが風景が少し違うような気が・・・。かなりの量の砂が移動しているのです。では、砂が積み増されてしまった位置に自生していた株は生き埋めなのかというと、時間を掛けてでも地上に顔を出すのだろうと思われました。それぐらいの根性はありそうです。
さて、今回は地下部を覗いてみようと、小さめの株の側を掘り起こしてみました。お判りいただけると思いますが、かなり深い位置まで真っ直ぐに根が伸びている。この程度の深さでも若干湿っており、小さな個体を維持する程度の水分は確保できるのだろうと思われました。大きな株では根も相当深くまで下りていて、十分な水分を確保しているということでしょう。でも、それ以上に、海水の浸食から身を守るために、大地にしっかり根付いている証拠なのだと理解しています。自生地を荒らさない程度にして、勿論、掘った穴は埋め直して帰りました。
2008/04/13
初めて、イソスミレの自生地を訪れた際、「これはオオタチツボスミレから進化した海岸性のすみれだ」と教わりました。確かに、大きさといい、距の色合い、花の形といい、外観的には良く似ています。しかしながら、2009年に京都府立大学生命環境科学研究科の細胞工学を研究する教授である平井正志氏が発表した研究成果によりますと、『(抜粋)全国のイソスミレの生育状況を調べ、サンプルを採取し、DNAのマイクロサテライトと呼ばれる部分の遺伝変異を調べ、系統関係を検討し・・・(中略)、オオタチツボスミレも変異の幅が小さく、イソスミレとは類縁が薄く、イソスミレとは別に進化したものと推定された』としています。
2013/05/18
以下の情報を見かけました。
~現在はイソスミレとセナミスミレは同一種とする見方が多いようだが、イソスミレよりやや遅咲きで、地下茎が長いものをセナミスミレとして39年に命名されているそうだ。(新潟日報「にいがた花語り セナミスミレ」に掲載とのこと)
植物園の方が執筆されているとのことですが、どの程度の信憑性がある内容なのか、確認する術がありません。個体差、地域差のレベルという印象があります。
2019/11/04


 、北海道:準絶滅危惧種、秋田県:絶滅危惧Ⅰ類、山形県:絶滅危惧Ⅱ類、新潟県:絶滅危惧Ⅱ類、富山県:絶滅危惧Ⅰ類、福井県:絶滅危惧Ⅱ類、京都府:絶滅危惧Ⅱ類、鳥取県:絶滅危惧Ⅱ類
、北海道:準絶滅危惧種、秋田県:絶滅危惧Ⅰ類、山形県:絶滅危惧Ⅱ類、新潟県:絶滅危惧Ⅱ類、富山県:絶滅危惧Ⅰ類、福井県:絶滅危惧Ⅱ類、京都府:絶滅危惧Ⅱ類、鳥取県:絶滅危惧Ⅱ類 , 小林 純子
, 小林 純子 が、イソスミレとは異なる種として発表したことから発生しているので悩ましい。現在はsynonymとして扱われている。
が、イソスミレとは異なる種として発表したことから発生しているので悩ましい。現在はsynonymとして扱われている。